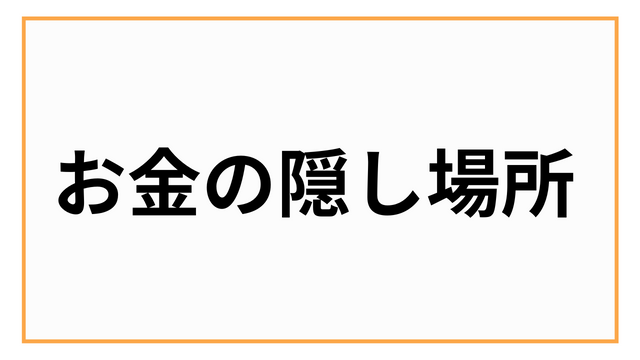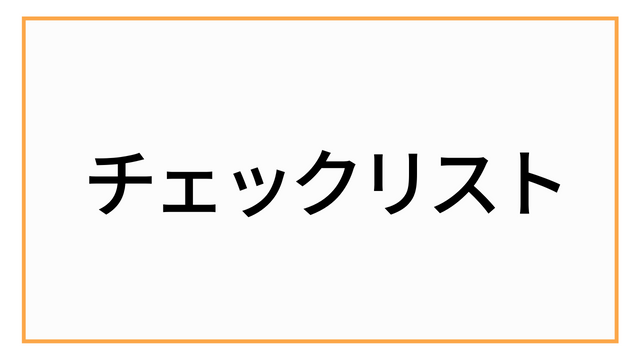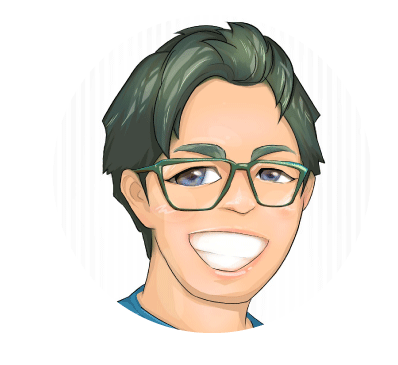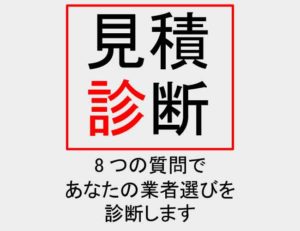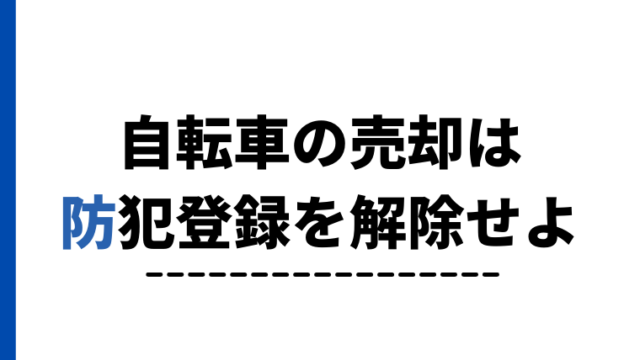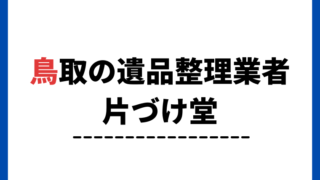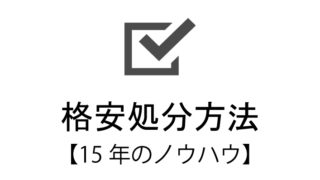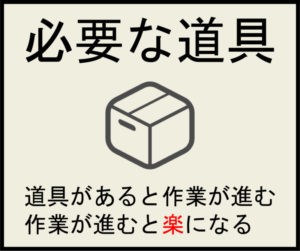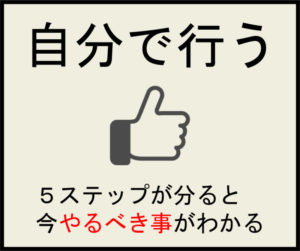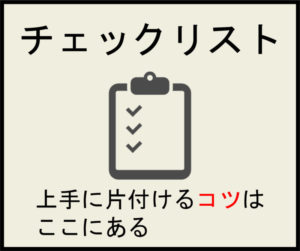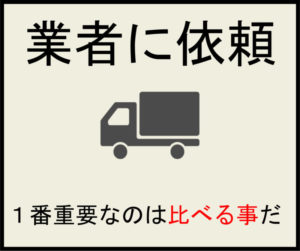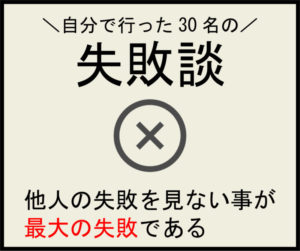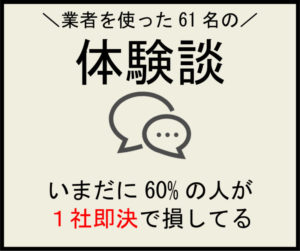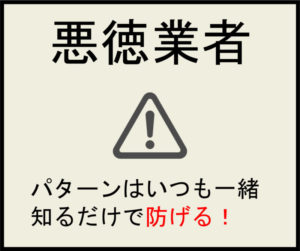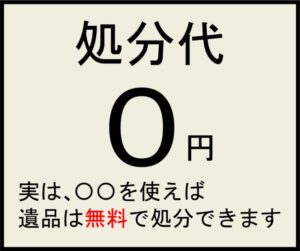遺品整理って荷物がたくさんあります
ってお困りの方も多いと思います
何時間片付けても一向に片付かないので途方に暮れてしまいます
結論からいうと
一向に片付かない人は動線の確保をおこなっていません
遺品整理業の片づけは普通の片づけと違います
ちょっとしたことですが、ポイントを押さえる事で作業効率がグーンと上がります
このページでは
プロが使っている6つのルールをご紹介します
この記事を読んで実行すると作業がはかどりますよ♪
【6つのルール】プロが使っている手順

① 作業効率を上げるため
動線には物をおかない
② 奥の荷物を搬出しやすくするため
玄関から近い部屋を整理していく
③ 疲れてモチベーションが下がるため
数人で作業する場合は同じ部屋で作業する
④ 作業の手を止めないため
迷ったら「保留」の段ボール箱に入れる
⑤ 探す時間を減らすため
テープなど良く使う物の置き場所を決める
⑥ 足の踏み場を確保するため
手前から奥
下から上へと整理していく
では一番大切なポイントから見ていきましょう↓
【手順1】動線の確保が一番大切

まず人や物が通れる道を作りましょう
そのために
玄関と廊下にあるものを
全部だして動線の確保が大切!
玄関には
物を置かないようにするのがポイントです
動線を確保せずに作業を進めると
ケガをする原因にもなります
通路や階段、ドアの手前には
物を置かないようにしましょう
途中で諦めた方のほとんどが
動線を確保せずに作業をしています
話を聞くと
どうにもならないから見積してください
とおっしゃいます
しかし
みなさん動線を確保せずに作業をしています
動線を確保しないと
たくさんの「無駄」が発生します
例えば通路に荷物があると
・壁や物を傷つける無駄
・荷物をよけて通る無駄
・足の踏み場を確保する無駄
が発生します。これではいつまでたっても終わりません
通路には物を置かないようにしましょう
他にも
効率良く片付けるルールがあります↓
【手順2】玄関から近い部屋から


片付けやすい部屋からではなく
玄関から一番近い部屋から片付けましょう
今回はわかりやすく
玄関から近い部屋と伝えましたが
部屋の状況にもよります
搬出時、トラックから一番近い部屋がベストです
①荷物の退避スペースができる
↓
②仕分けることが出来る
↓
③荷物の置く住所ができる
↓
次の部屋の片づけが楽になる
「荷物の住所」を作ることがポイント
もし一番奥の部屋から行うと
手前の荷物をよけならがら作業することになります
【手順3】一部屋づつ片付ける
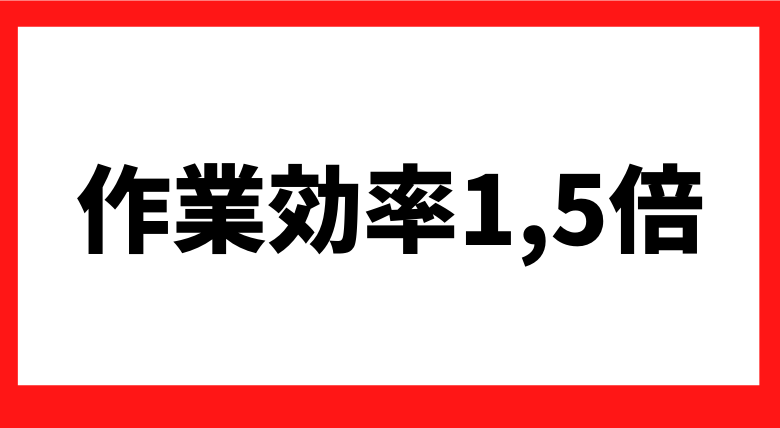
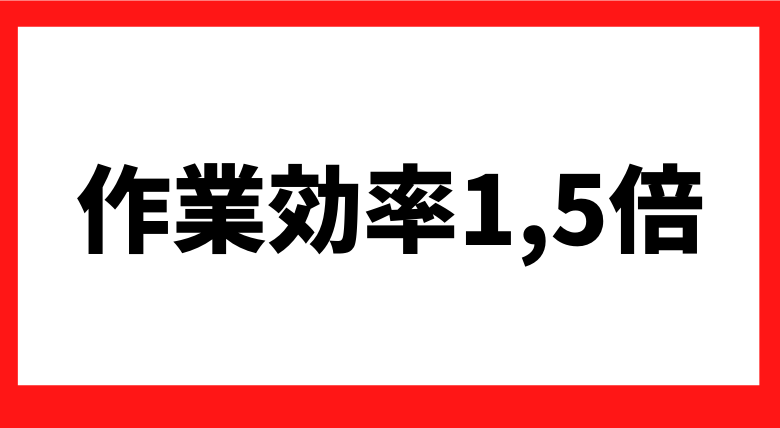
遺品整理は集中力と持続力が必要です
・気分転換になる
・協力が得られる
・作業効率があがる
・進捗状況がわかる
一人で黙々と仕分け作業をしていると気分が滅入ってきます
私の会社では複数人で作業する場合は、一人ではなく必ず二人ペアで片付けるようにしています。
一人では物を運べない時などすぐに協力を得る事ができるので作業効率が上がるからです
また一部屋づつ片付けていくと進捗状況が分りやすいのです
「今日は3部屋を片付けた!」っていう達成感も得られるのでモチベーション維持にも役立ちます
【手順4】保留ボックスを使用する
遺品整理中はとても大変です
作業時間がとれない人は時間との勝負でもあります
自分で判断して
必要な物、不要な物を決めなければいけません
しかし中には迷ってしまう物もでてきます
特に女性は手が止まりやすいです
昔の写真や思い出の品物が出てきたらもう完全に手が止まってしまいます
そこで保留ボックスや保留スペースを作りましょう
・作業の手が止まらない
・他の家族に確認ができる
・冷静な時に判断できる
遺族でしか判断できない物がでてきたらそこに保留して後で確認してもらっています
保留ボックスを作ると、作業中に手が止まらなくなるのでオススメです
【手順5】道具も置く場所を決める
道具を置く場所を決めておかないと
作業中に
ってなることが多々あります
・道具を探す時間の削減
・集中力がきれない
当社では家の中心の部屋に道具を置くようにしています
【手順6】足場を確保する

片付ける順番として
①の写真の場合だと足元をまず片付けましょう
その次に②の奥の家具など
そして最後に③の家具の上にのっているものを片付けると効率が良いです
・引っ張りださなくて良い
・足元を確保できる
・ケガのリスクを避ける
まとめ:遺品整理を自分で行う片付け手順 片づけがはかどる6つのルール
① 作業効率を上げるため
動線には物をおかない
② 奥の荷物を搬出しやすくするため
玄関から近い部屋を整理していく
③ 疲れてモチベーションが下がるため
数人で作業する場合は同じ部屋で作業する
④ 作業の手を止めないため
迷ったら「保留」の段ボール箱に入れる
⑤ 探す時間を減らすため
テープなど良く使う物の置き場所を決める
⑥ 足の踏み場を確保するため
手前から奥
下から上へと整理していく
参考にしていだけたら幸いです
それでは!